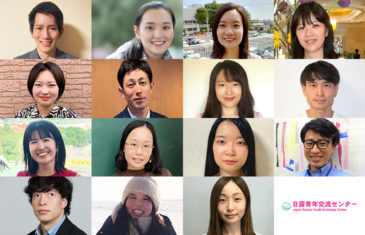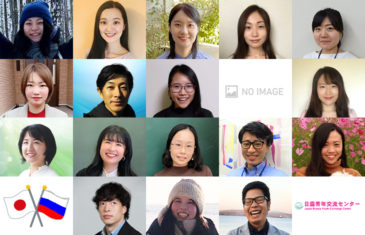-滞在記- 若手研究者等フェローシップ( 2012 年度)
アレクセイ・レヴィンスキーのこと 伊藤 愉
2013年10月3日から5日にポーランドのヴロツワフで開催された国際メイエルホリド学会の企画の一つに「ビオメハニカ・ワークショップ」があった。ワークショップのある場面で音楽を使っていたレヴィンスキー氏に、観客の一人が「あの音楽の意味と俳優の身体の関係を教えてください」と訊ねると、レヴィンスキー氏は「そういうつながりを特に考えていたわけではなく、音楽はただの要素だ」と答えた。
ビオメハニカとは20世紀前半のロシア人演出家フセヴォロド・メイエルホリドが考案した俳優訓練です。生体力学とも訳すことができるこの訓練方法は、俳優の身体的構図に着目し、空間における身体の在り方から感情を導きだす、あるいは反射的に(または即興的に)演劇空間における次の行為を導くことを目的としていました。 レヴィンスキー氏は、ロシアで「スタニスラフスキーの家の側」劇場で俳優・演出家として活動しながら、モスクワを中心に様々な場所でビオメハニカを教えている。かつてメイエルホリド劇場で働いていたニコライ・クストフの元でビオメハニカを学んだ彼は、メイエルホリド直系の指導者と看做されている。
ロシア滞在中に一年ほど彼が教えるワークショップに参加して、私もビオメハニカを学んだ。彼は普段、必要以上に言葉を足さない。メイエルホリドはまとまった演劇論を残しておらず、それゆえに現代でもビオメハニカがどういうものだったか議論は尽きない。レヴィンスキー氏はそうした状況に対して、答えを用意するのではなく、素材としてビオメハニカの実践を提供しているように思える。彼は指導中も教え子たちと一緒に身体を動かし、一緒にエクササイズを行い、身体のポーズの一つ一つを細かく調整する。
ある時、書いた論文をレヴィンスキー氏に読んでもらおうと思って、電子メールで原稿を送った。数日後、電話がかかってきて、劇場までおいで、と言われた。劇場のとなりにある事務局の前で待っていると、猫背中のレヴィンスキー氏が現れて事務棟の上階にある楽屋まで案内してくれた。この劇場は、もともとあった大きな舞台が、数年前の火事で焼け落ちてしまい、いまは小舞台でのみ上演している。楽屋に上がるまでの階段の窓から、隣り合う建物の壁に囲まれた焼け落ちた大舞台の跡が見えた。「建て直さないんですか?」と訊くと、「いろいろ問題があってね」と彼は言う。「ほら、隣の建物を見てごらん、きれいな窓だろ。お金持ちが住んでいる。彼らはね、また劇場なんかが隣に出来るのを嫌がっているんだ」と。財源も豊かでないうえに近隣住民の反対もあって、火事にあった跡はそのままに置かれている。こうした空っぽの空間がモスクワにはいたるとこにある。そこかしこに何も待っていない抜け落ちた空間がある。モスクワの市民に愛された演劇文化も、いつまでも全ての人が求めるわけではない。いつかはただの空間になる。とても悲しいことだと思う。
レヴィンスキー氏は、私の論文を読んで、「面白いけど、まだ途中だね」と言った。「もっと発展させられるよ」と言い、現代音楽が好きな彼は「この演劇の音楽理論のところとかジョン・ケージの理論とぴったりだと思うんだけど、どうだろう?」と肩を揺らしながらくしゃっと笑う。
「スタニスラフスキーの家の側」劇場では、若手の俳優達を中心に、レヴィンスキー氏の指導のもと、継続的にビオメハニカの訓練が行われている。最近、劇場の舞台で一つの演目としてビオメハニカのエチュードを公開した。

「スタニスラフスキーの家の側」劇場でのビオメハニカの上演
劇場に所属する知人の俳優に、「ビオメハニカって役に立つ?」と訊ねると、少し困った顔をして「実ははっきりとは分からないんだ」と答えた。それから、「でも、身体の置き方が分かるようになった」と面白い表現を使った。舞台に立つと言うことは、誰かに見られるということだ。観客との距離感、舞台上の空間における身体の位置。そうしたことに無自覚な俳優は、板の上でまっすぐに歩くことができない。空間に身体を置く感覚を知ることは、俳優にとって大変重要なことなんだろう、と思った。
件の国際学会のワークショップでは、レヴィンスキー氏の他に、ゲンナジー・ボグダノフ氏も指導を行っていた。ボグダノフ氏もニコライ・クストフの教え子の一人だ。レヴィンスキー氏のある意味単調なエクササイズに対して、ボグダノフ氏の指導は、独自の解釈を加え、より現代的に再構成された、見ていて楽しいものだった。一方で、クストフの教えを受けてから少しも内容を変えることなく淡々とビオメハニカの訓練を続けるレヴィンスキーの誠実さと実直さにはやはり心が躍る。リズムや構成(コンポジション)というタームと深く結びつく「音楽」は、ビオメハニカを生み出したメイエルホリドにとって大変重要な概念であり、だからこそ観客の一人は「なんのために」と問いかけたのだが、レヴィンスキー氏は「ただの要素」以上の意味を付け加えない。サミュエル・ベケットの作品を愛する彼は、自分の口から言葉が一人歩きをして、見事な物語を紡ぐことを拒む。あたかも、彼自身がベケットの登場人物のようだ。だからこそ、彼のそうした態度を信頼したいと思う一方で、彼の気持ちへ寄り添うことの難しさも感じさせる。
客席ですぐ後ろに座っていたペテルブルグの著名なメイエルホリド学者が隣にいるモスクワ芸術学研究所の演劇学者と、「レヴィンスキーのほうが本来のビオメハニカだよね?」、「そうそう、ボグダノフのほうはかなりアレンジしている」と囁き合っていた。メイエルホリド研究を何十年も続けている彼らの暢気な会話に気が和む。研究をしていると、いつの間にか意味を求めてしまう。考えているうちに、大変な過ちかもしれないという怖れを失う。これは、考えながら、考えることをやめる行為かも知れない。レヴィンスキー氏の「ただの要素」という言葉は、安易な解釈に距離を置く。それでも、私は彼の言葉から、意味を汲み取ろうとしてしまう。それが研究者と実践者の関係なんだろうか。
ヴロツワフのワークショップの後、レヴィンスキー氏のもとに行き、モスクワに帰ったら、記録を取るためにワークショップを見学させて欲しいと伝えた。彼は柔和な顔をして、「電話して。またモスクワでね」と言った。

自分のスタジオの生徒達にビオメハニカの指導をするレヴィンスキー氏(一番右)
日露青年交流センター Japan Russia Youth Exchange Center
このページの文章、画像等一切の無断使用を禁止します。また、リンクを張る際は必ずご連絡下さい。
All right reserved, Copyright(C) Japan Russia Youth Exchange Center 2000
関連タグ
オススメ記事
All right reserved, Copyright(C)
Japan Russia youth Exchange Center 2000-.