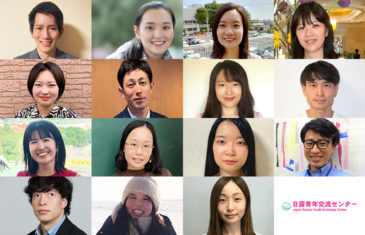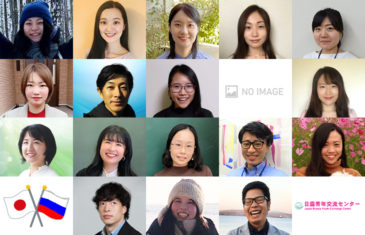-滞在記- 若手研究者等フェローシップ( 2014 年度)
モスクワ裁判傍聴記 佐藤史人
法学の研究者にとって、現地滞在の魅力の一つに法適用の現場を目にすることができるという点がある。その最も簡便な手段の一つが、裁判傍聴であろう。私も、ロシア法研究者の先達の例に倣い、これまでのモスクワ滞在中に何度か裁判を傍聴した。私が主に訪問するのは、モスクワ市北東部にあるモスクワ市裁判所である。この裁判所は、連邦最高裁の一つ下のレベルの裁判所であり、刑事裁判では、加重事由のある殺人罪などの重罪事件の第1審、市内の地区裁判所が第1審裁判所として審理した事件の控訴審などを管轄している。陪審裁判が行われるのもこの裁判所である。今回は、これまで傍聴した裁判のうち、特に印象に残った事例を紹介したい。
この6~7年ほど、日本のロシア法研究者は、ヨーロッパ人権裁判所(以下、「人権裁判所」という。)の判決のロシアへの影響に関心を寄せている。ロシアを被告国とする人権裁判所の判決が初めて言い渡された2002年以降、人権裁判所の判決によりロシアの司法制度における数々の構造的問題が指摘され、そうした問題の一部は、制度改革の対象にもなっている。そのような問題の一つに、勾留手続がある。かつてロシアの裁判所は、勾留請求がなされれば、ほとんどの場合にそれを認めていた。また、裁判所が勾留の延長請求を審理する際にも、被告人の置かれた具体的な事情はほとんど考慮されなかった。すなわち、それぞれの事件においてなぜ勾留の延長が必要になるのかを具体的事実をもとに証明することを怠り、事件における犯罪の重大性、被告人による証拠隠匿や逃亡などの抽象的可能性を根拠として挙げるだけの訴追側の対応を、裁判所は基本的に是認していたのである。しかし、このような態度は、人権裁判所から「過度の形式主義」であり、人権侵害にあたると認定されたため、2003年に刑事訴訟法典が改正された。改正後の関連条文が、裁判所が勾留を認める際には「裁判官が当該決定を下す根拠となった具体的な事実を記載しなければならない」と規定するのは、上記の趣旨に基づくものである。この法改正後、実務はどう変わったのだろうか。例えば、2011年に2010年のモスクワ市裁判所の活動を総括したエゴロヴァ所長の報告では、勾留請求却下率が以前に比べて高くなったと指摘されている。このように、上記の改革の成果を肯定的に語る見解もみられるものの、はたして実務が本当にヨーロッパ人権条約の趣旨に則って運営されているのだろうかという点について、私は長らく疑問を持っていた。
そうしたなか、今年の2月末に傍聴した裁判は、私の疑問に対して一定の回答を示すものとなった。問題の裁判は、20人以上が亡くなった2014年7月のモスクワ地下鉄事故に係わるものである。といっても、傍聴したのは、当該事件の被告人が有罪であるか、無罪であるかを問うものではない。今回傍聴したのは、上記の事件の被告人4名による保釈請求が裁判所に認められなかったため、裁判所の決定に対して被告人から提起された不服申立を扱った裁判である。
裁判当日の午前中、私は、現地調査のために訪露した日本人研究者の一行とともに、人権裁判所について知悉するロシア人弁護士からの聞き取り調査に参加していた。その際、たまたま同弁護士より自らが弁護人を務める裁判がこの後行われる予定であるとの話が出たため、調査の参加者一同で、急遽、その裁判を傍聴することにした。裁判は、12:00に開始予定のところ、同じ法廷を使った前の裁判が長引いたために予定より1時間30分遅れて始まった。法廷でまず興味を引かれたのは、保釈請求をした被告人が直接には出廷せず、ネットを通じて(おそらくは拘置所から)審理に参加したことである。また、訴追側として出廷した取調官(следователь)と検察官のうち、検察官が法廷において制服やスーツではなく、スタジアム・ジャンパーを着用していたことにも驚いた。
今回の裁判で特に印象に残ったのは、次の二点であった。第一は、被告人が、自分たちは市民感情を満足させるためのスケープゴートにされたとの立場から、訴追側に対峙した点である。捜査関係者は事件の全容を解明し、真に処罰されるべき者を明らかにすべきであるにもかかわらず、それを怠り、自分たちはその代わりの手頃な有責者として仕立てあげられたというのが、彼らの主張であった。被告人たちは、裁判官から発言の機会を与えられると、それぞれに堂々たる調子で自らが無罪であると主張し、取調官の不当な態度を批判した。その姿はまるで演説のようであった。ある者は、「われわれは実験動物ではない。逃げも隠れもしない、なぜ勾留するのか」と問い、別の者は、刑事事件における適法性の遵守を裁判官、検察官、取調官に求める刑事訴訟法典17条を読み上げて、公正な裁判が行われるよう要求した。彼らの主張の真否はともかくとして、私は、被告人のこのような姿を目にしながら、19世紀後半のロシアの陪審裁判を思い出していた。帝政期には、テロ事件などの政治的事件や上流貴族のスキャンダラスな事件などが陪審法廷に係属し、裁判所に傍聴人が押し寄せた結果、裁判所が「劇場」と化した時代があった。そこで公衆の興味を引いたのが、法廷での弁護人や被告人、検察官による丁々発止の「演説」であり、時には「演説」の力によって権力犯罪の被告人に対し無罪評決がなされることすらあった。もっとも、我々が目にした現代の裁判では、傍聴人は、われわれ日本人の法学者を除けば、被告人の親族・同僚とおぼしき数人と、メディア関係者と思われる一人の若者に過ぎなかったが。
第二に印象深かったのが、保釈の是非の根拠である。私が法廷でのやり取りを聞いて理解した限りでは、訴追側は保釈を拒絶するだけの十分な理由を示さなかった。取調官は保釈請求の却下を求めながら、その理由として挙げたのは、逃亡の恐れや証拠隠滅(被告人による同僚に対する圧力など)の可能性といった具体性に乏しい根拠のみであった。一方、5,6人の弁護士からなる弁護団は、ヨーロッパ人権条約と人権裁判所の判例などを援用してこれに応戦した。このように、事件の焦点は、かつて人権裁判所が指摘したロシアの勾留に関する実務の核心的問題と同一の論点に関わるものであった。しかし、裁判所が最終的に下した判断は、被告人側の不服申立を退け、彼らの勾留を続けるというものだった。ちなみに、同行した日本人研究者に後から聞いた話では、弁護人の話が人権条約に及んだ際に、裁判官は嫌そうな顔をしていたという。
裁判後、裁判官が去った法廷では、法廷と拘置所とを結ぶネット回線が直ちには切断されなかったため、モニターを介して拘置所にいる被告人と法廷にいる傍聴人、弁護団の間である種の「交歓」が行われていた。彼らが、互いに激励し、今後の裁判における奮闘の意思を固め合あう姿は、私にとって非常に心に残る情景であった。
今回の裁判では、被告人が起訴の不当性を全面的に争う事件であったがゆえに、それをどこまで一般的な傾向と言えるかはともかくとして、人権裁判所の判決の趣旨がいまだロシアの国内裁判所において徹底されているとは言い難いということを強く印象づけられた。また、裁判所からの帰途、その日の法廷の情景が頭に浮かび、当事者の、裁判官の、取調官の発言とその際の雰囲気とその際に感じた印象とを自然と心の中で反芻していた。以前にモスクワ大学において非法学分野の教員と話をした際に、その教員は法学文献を形容する言葉として「乾いた」という表現を使っていたが、裁判傍聴には、そのような「乾き」を癒す効果があるように思う。すなわち、私にとって、この日の裁判傍聴は、無味乾燥な専門用語で展開される法適用の背後に、血の通った人々の生活があり、様々な思い、感情、信条が渦巻いていることを改めて確認する良い機会となった。

傍聴日のモスクワ市裁判所
日露青年交流センター Japan Russia Youth Exchange Center
このページの文章、画像等一切の無断使用を禁止します。また、リンクを張る際は必ずご連絡下さい。
All right reserved, Copyright(C) Japan Russia Youth Exchange Center 2000
関連タグ
オススメ記事
All right reserved, Copyright(C)
Japan Russia youth Exchange Center 2000-.